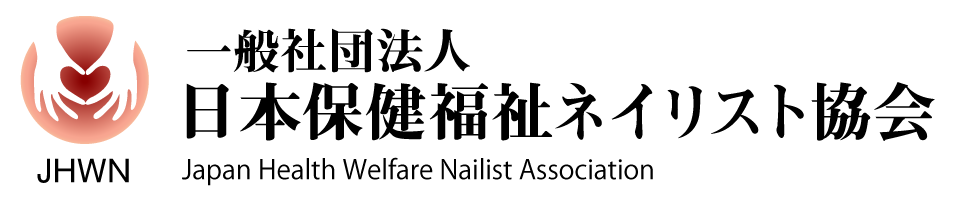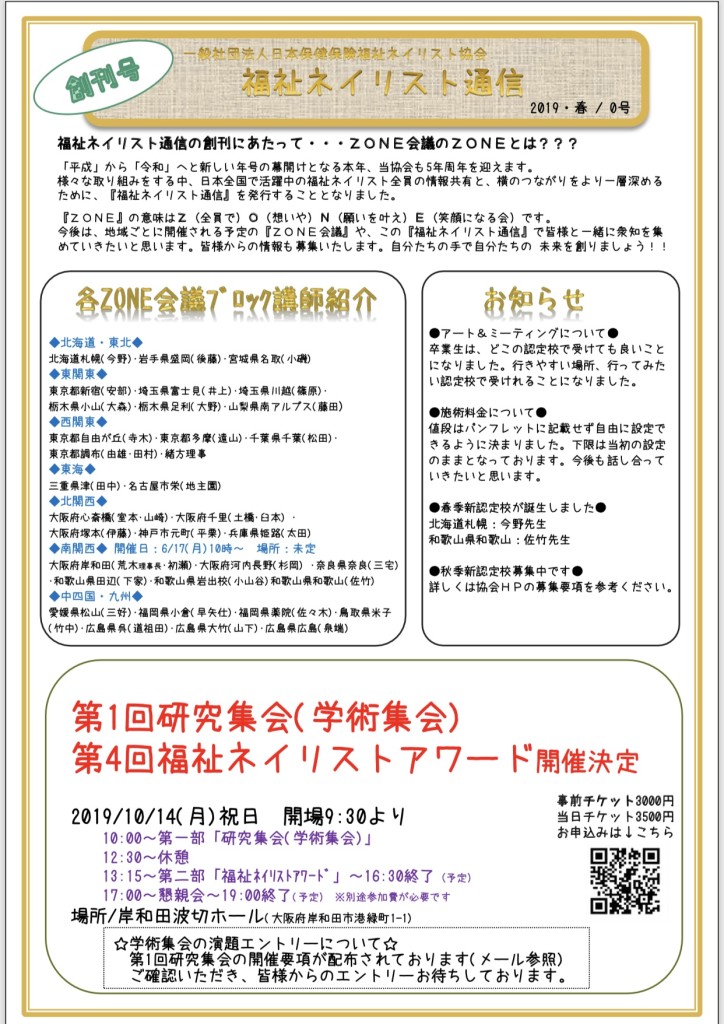介護報酬の仕組みとは?ネイルで加算算定の実例もご紹介!

厚生労働省によると、日本では令和2年10月1日時点で介護サービスを行っている事業所が71,555事業所、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの介護保険施設では13,702施設までに増えているという調査結果があります。
超高齢社会の日本において、介護を必要とする高齢者を支えていくためのサービスや介護保険施設は必要不可欠です。そんな介護保険サービスを提供する事業所・施設では「介護報酬」を算定することによって事業収入を得ています。
介護報酬の加算が算定されるサービス内容はさまざまで、近年では、認知症高齢者に対してネイルを施すことで加算が算定されている例もあるのです。
今回は、介護報酬はどのような仕組みになっているのか、実際にどんなサービスに対して加算が設けられているのか、ネイルで加算が算定された実例をご紹介していきましょう。
介護報酬の基本的な仕組み
介護報酬とは、デイサービスや介護老人保健施設などの事業者が利用者にさまざまな介護サービスを提供することで、その対価として得られる報酬のことです。基本的に、介護報酬の7~9割は介護保険から支払われ、1~3割が利用者の自己負担となります。得られた介護報酬が事業所の主な事業収入となり運営されているのです。
介護事業所を運営する上で重要な介護報酬は、「基本報酬」と「加算」「減算」という仕組みで構成されています。これらは、事業所が提供するサービスの内容・体制や利用者の状況に応じて算定されます。
そのため、施設の種類や専門職員の配置、提供しているサービスによって、各々の事業所がどれだけ介護報酬を算定しているかは異なります。また、介護報酬は3年毎に改定されるため、世の中の情勢や利用者の要望に合わせて事業所は提供する介護サービス内容を日々見直していく必要があるのです。
介護報酬加算の例
介護報酬では、人員の配置や提供するサービス内容、利用者の状態などで細かく加算・減算が設けられています。介護報酬では、それぞれに決められた点数を「単位」として示します。地域によって1単位の単価は若干異なりますが、基本的には1単位=10円として報酬を計算することができるのです。
その中でも、介護老人保健施設における食事場面に関わる加算と認知症に関する加算をご紹介しましょう。
食事場面に関わる加算
 |
|
食事は生きるためにとても重要な行為であり、命とも直結しています。そのため、食事を提供することだけでなく、栄養面におけるマネジメントや食べる能力を維持するために専門職が関わるための加算、衛生面における加算など、多くの加算項目が用意されています。
認知症に関する加算
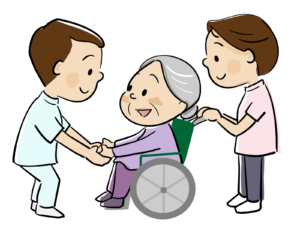 |
|
介護施設において、認知症の方へのケアも必要不可欠となっており、認知症に対する専門的な知識を有するスタッフを配置することで、ケアの質の向上が求められています。そのため、認知症に関する加算項目も徐々に増えてきている実状があるのです。
加算を算定するメリットは利用者にもある
事業所を運営するにあたって、介護報酬を算定していくことは安定した事業収入を得るために重要なことです。しかし、事業収入を増やすためだけに事業所は加算を算定しているわけではありません。
定められたそれぞれの基準やサービス内容を満たし、介護報酬の加算を増やしていくことは、その事業所の介護の質を高め、利用者・家族にとってより求められる場所になるということでもあるのです。
それは逆を言えば、その事業所・施設を利用する利用者・家族にとっては、より充実した細やかな介護サービスを受けられるという証でもあります。大事な家族を施設に預ける上で、預け先の施設がどれだけの加算を算定しているかは施設選びの基準の一つになり得るかもしれません。
ネイルで加算算定した実例紹介
介護が必要な方に対する食事や入浴、排泄、整容のケアやリハビリを専門職種が行った際に介護報酬の加算が算定されますが、近年では、ネイルという福祉美容を行った場合にも介護報酬の加算が算定されている実状があるのをご存知でしょうか。
そんな介護の現場にネイルが導入されている実例を一部ご紹介いたします。
| 対象施設 | 介護老人保健施設(通称:老健) |
| 算定した加算名 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(240単位/日) |
| 対象利用者様の条件 |
|
| 実施した職員 | 福祉ネイリストの資格を持った作業療法士 |
| 実施した内容 | 20分間の介入の中で、マニキュアでネイルカラーを施しながら回想法を用いた会話を実施。施術環境は周囲には他の利用者がいない静かな場所を選び、1対1でネイル介入や回想法介入に集中できる環境設定を行った。 |
| 実施した結果 | 実施直後では、表情の変化(笑顔が増加)や他の利用者に対するコミュニケーション量が増加した。また、ネイル介入を継続することによる変化としてBPSD(認知症の行動・心理症状)でも代表される徘徊や不安を訴える回数が減少する結果が示された。 |
【実際にネイル介入した際の様子】
このように、実際に介護現場にネイルという福祉美容を取り入れて、認知症の方へのリハビリテーションを行い、介護報酬の加算を算定している施設もあります。実際に近年では、認知症の方へ与えるネイルの効果についてもさまざまな研究がされているのです。
第27回全国介護老人保健施設大会 大阪にて演題発表された研究:『認知症高齢者を対象としたマニキュア介入の効果』
公益社団法人 全国老人保健施設協会 全国大会演題登録システムより
今後の可能性
日本では年々高齢者の人口は増加し、地域包括ケアシステムの推進や認知症高齢者への対策に力が注がれています。3年毎に改定される介護報酬の算定要件を見ても、自立支援に向けたリハビリテーションの実施や介護ケアの質の向上が求められているのです。
介護分野の人材不足の問題は常々叫ばれている中で、科学的介護を構築することでの効率化も大事です。しかし一番忘れてはいけないことは、歳を重ねても、介護が必要となっても、一人ひとりの尊厳を守りながらその人らしく生きていける世の中をつくることではないでしょうか。
福祉美容は今、さまざまな取組みが介護の現場でも取り入れられています。日本保健福祉ネイリスト協会では、ネイルに関する研究集会が開催され、認知症高齢者へのネイル介入による効果なども少しずつ根拠として示されつつあります。それは、福祉美容の可能性を信じて取り組む専門職種、そして、介護の現場で利用者様のためにと日々励まれているスタッフ方の想いの証なのです。
今後、介護分野でもネイルなどの福祉美容が当たり前に存在し、ネイル介入による介護報酬の加算算定が広まることで、介護を必要とする方がその人らしく生きるための一助となり得るのではないかと期待したいです。
【参照サイト】