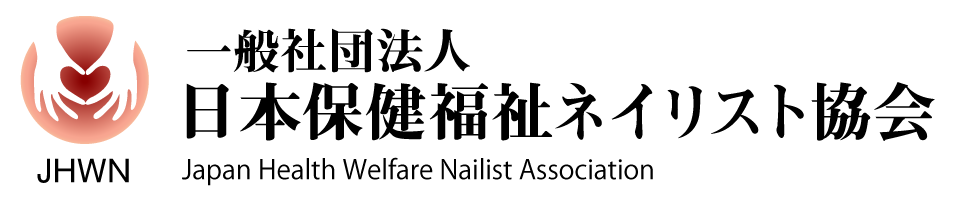セラピーとは?種類や効果、セラピストに向いている人の特徴を解説!

「セラピー」と聞くと、メンタルケアのイメージが強いですが、実はさまざまな種類があることはご存じでしょうか。
セラピーには、医療的なものからリラクゼーションを目的としたものまであり、近年では複数の手法を組み合わせた統合的なアプローチも注目されています。
また、セラピーは受ける側だけでなく提供する側にとっても大きなメリットがあり、やりがいのある仕事として人気です。
本記事では、そんなセラピーの目的や種類、向いている人の特徴を詳しく解説します。セラピーの仕事に興味のある方はぜひ参考にしてください。
目次
セラピーとは?
セラピー(Therapy)とは、心や身体の不調を改善し、健康をサポートするための療法や施術のことを指します。語源はギリシャ語の「therapeia」に由来し、本来は「治療」や「療法」を意味するそうです。
現在では、病気の治療だけでなくリラクゼーションやメンタルケア、自己肯定感向上など幅広い目的で活用されており、それぞれに適したセラピーの種類があります。
セラピーの目的・効果
セラピーの目的は、薬や手術などに頼らず自然な方法で心や体の健康を回復・維持し、より良い生活を送ることです。具体的には、以下のような効果を得るためにセラピーを行います。
- リラックスした状態を促す
- 体の痛みを和らげ健康を維持する
- ケガや病気による身体機能の低下を回復する
- ストレスや不安、鬱症状を和らげる
- 感情をコントロールできるようにする
- 人間関係の改善を助ける
- 自分自身を深く理解して自信を持つ
- 生活に覇気を与える
上記からも分かるように、セラピーは心身のリラックスとストレス軽減のために施されることがほとんどです。とくにマッサージやアロマセラピーなどはお店で気軽に受けられるため、日々のストレスの解消に利用する方も多いでしょう。
また、不安や抑うつ状態の改善もセラピーの重要な目的の一つです。精神的な不調や悩みを抱える人にとって、心理カウンセリングなどのセラピーは心を整える大きな助けになります。
ほかにも、日常に彩りを加えポジティブな気持ちを育むことができるカラーセラピーや音楽セラピーを生活に取り入れたり、体に痛みや不調を感じる場合は整体やお灸を、ケガや病気による筋力低下にはヨガやピラティスといった運動療法を取り入れることもあります。
セラピーは提供する側にも良い影響がある
セラピーは、セラピーを受ける側だけでなく提供する側にとっても多くのメリットがあります。
具体的には、セラピーを学ぶことでストレスを軽減する方法を身につけたり、セラピストとしての道が開けるといったことが挙げられるでしょう。
さらにセラピストとして活動すれば「人の役に立っている」「社会に貢献している」と実感しやすくなり、自信や自己成長にもつながります。
セラピーの種類
セラピーにはさまざまな種類がありますが、どのセラピーも人々の健康や心の安定を支える重要な役割を持っています。ここでは、それぞれの特徴や方法について詳しく解説します。
種類1. 医療系セラピー
医療系セラピーは医療の分野で用いられており、病気やケガの治療、機能回復、痛みの軽減、そして生活の質(QOL)の向上を目的としています。
症状や目的によって多様なセラピーの中から最適な方法を判断する必要があるため、医療資格を持つ専門家が施術することがほとんどとなっています。
また、単に病気を治したりリハビリのためだけに行われるものではありません。患者がより快適に過ごせるよう、心身のバランスを整えることも大きな目的としているため、心理的なサポートも重要視されています。
代表的な医療系セラピー
理学療法(Physical Therapy)
理学療法は、主に運動機能の回復を目的としたセラピーです。病気やケガ、加齢による身体機能の低下を改善するために、運動療法や電気療法、温熱療法などが用いられます。国家資格である理学療法士(PT)が担当し、個々の対象者の状態に合わせたリハビリプログラムを提供します。
作業療法(Occupational Therapy)
作業療法は、日常生活の動作や社会生活をスムーズに送るための訓練を行うセラピーです。事故や病気、発達障がいなどによって生活動作に支障が出た人を対象に、手や指の動きを改善したり、日常生活での応用的な動作を訓練します。国家資格である作業療法士(OT)が専門的に対応し、対象者が自立した生活を送れるよう支援します。
言語聴覚療法(Speech Therapy)
言語聴覚療法は、話すことや飲み込むこと(嚥下)に問題がある人をサポートするセラピーです。脳卒中後の言語障害や、発達障がいによる言葉の遅れ、吃音などに対して、国家資格である言語聴覚士(ST)がリハビリを行います。また、食べ物をうまく飲み込めない嚥下障害に対するトレーニングもこのセラピーの一環です。
種類2. ボディ系
ボディ系セラピーは、身体のケアやコンディショニングを目的としたセラピーです。筋肉や関節、血流、リンパの流れなどに働きかけ、痛みやコリの改善、リラクゼーション、身体機能の向上を目指します。
施術方法としては手技によるマッサージ、ストレッチ、矯正などが多く、基本的には「身体への直接的なアプローチ」が特徴です。
医療系セラピーほど厳密な資格要件はありませんが、専門的な技術や身体の仕組みについての知識が必要となるため、スクールや専門講座で学ぶことが推奨されます。
代表的なボディ系セラピー
マッサージセラピー(Massage Therapy)
マッサージセラピーは、手技によって筋肉をほぐし、血行を促進するセラピーです。リラクゼーション効果が高く、ストレス解消にも役立ちます。マッサージの種類にはさまざまなものがあり、スウェディッシュマッサージ、ディープティシューマッサージ、タイ古式マッサージなど、手法や目的に応じた施術が行われます。
リフレクソロジー(Reflexology)
リフレクソロジーは、足裏や手のひらにある反射区(末梢神経が集まる場所)を刺激することで、全身の不調を整えるセラピーです。特に足裏のリフレクソロジーは、内臓の働きを活性化し、血行促進やデトックス効果が期待できます。手技による施術が一般的ですが、専用の器具を使う場合もあります。
カイロプラクティック(Chiropractic)
カイロプラクティックは、背骨や骨盤の歪みを調整することで、神経や筋肉のバランスを整えるセラピーです。特に、腰痛や肩こり、頭痛などの症状を改善する効果が期待されます。専門的な知識が必要なため、施術を行うには資格やトレーニングが必要となることが多いです。
種類3. メンタル系
メンタル系セラピーは、心の健康をサポートすることを目的としたセラピーです。ストレスや不安、うつ症状、人間関係の悩みなど、精神的な問題にアプローチし、心のバランスを整える役割を果たします。
セラピーの手法にはさまざまな種類があり、心理学の理論を基に心の問題を解決へ導く心理療法や、相談者の悩みに耳を傾けて心の整理をサポートするカウンセリングなどが一般的です。
また、音楽や絵画などを通じて心を癒す芸術療法もあります。いずれの方法も単に心を癒すだけでなく、自分自身と向き合い、より良い生き方を見つける手助けとなるでしょう。
なお、メンタル系セラピストを目指すには、専門的な知識や技術の習得が必要です。代表的な資格として公認心理師(国家資格)や臨床心理士(民間資格)があり、これらを取得するためには心理学の基礎知識を学び、カウンセリング技法を身につけなければなりません。
代表的なメンタル系セラピー
心理カウンセリング(Psychological Counseling)
心理カウンセリングは、相談者が抱える悩みや問題に対して、対話を通じてサポートするセラピーです。カウンセラーは対象者の話を傾聴し共感しながら、問題の本質を整理して解決に向けた気づきを促します。カウンセリング方法としては、認知行動療法、来談者中心療法、精神分析などさまざまなアプローチがあり、相談者の状態に応じて適切な方法が選ばれます。
芸術療法(Art Therapy)
芸術療法は、絵を描いたり、音楽を演奏したりすることで、心の内面を表現し、感情を解放するセラピーです。特に、言葉で気持ちを伝えることが苦手な人や、心の奥深くにある感情を整理したい人に適しています。絵画療法、音楽療法、ダンスセラピーなど、さまざまな形があり、心理療法の一環として活用されることもあります。
種類4. リラクゼーション系
リラクゼーション系セラピーは、心身のリラックスを目的としたセラピーです。不眠や肩こり、頭痛、消化不良など、さまざまな不調の原因となるストレスや疲労を軽減したり、予防的なケアとしても利用されています。
セラピーの手法としては、香りによって心を落ち着かせるものや、身体のこわばりをほぐして深いリラックスへと導くもの、温めることで血流を促し疲労回復を助けるものなどさまざまです。さらに、動物との触れ合いや美容を通じたケアによって心の安らぎや自己肯定感を高め、前向きな気持ちへと導くセラピーもあります。
リラクゼーション系のセラピーを学ぶ場合は、専門のスクールに通い、民間の認定資格を取得することが一般的です。セラピーの種類によっては資格必須というわけではありませんが、より深い知識と技術を持ったうえで施術をした方が、利用者の満足度も高くなるでしょう。
代表的なリラクゼーションセラピー
アロマセラピー(Aromatherapy)
アロマセラピーは、植物の精油(エッセンシャルオイル)を活用し、香りの力でリラックスやリフレッシュを促すセラピーです。精油にはリラックス効果のあるラベンダーやカモミール、集中力を高めるローズマリー、気持ちを明るくする柑橘系の香りなどさまざまな種類があります。アロママッサージやディフューザーを使った芳香浴など、日常的に取り入れやすいのも魅力です。
温熱療法(Thermotherapy)
温熱療法は、温めることで血流を促進し、筋肉のこわばりを和らげるセラピーです。岩盤浴、ホットストーンセラピー、よもぎ蒸しなど、さまざまな方法があります。特に、冷え性や肩こり、慢性的な疲労を抱える人に適しており、身体を芯から温めることで深いリラクゼーションが得られます。
福祉ネイル(Welfare Nail Therapy)
福祉ネイルは、高齢者や障がいのある方に向けたネイルケアを提供するセラピーの一種です。通常のネイルとは異なり、美しさだけでなく、手や爪を清潔に保つケアや、施術を通じたコミュニケーションによる心のケアが重視されます。また、ネイルケアを受けることで、自分の手元が美しく整えられるだけでなく、気持ちが明るくなり、自信を持つきっかけにもなります。
セラピストの仕事が向いている人
セラピストの仕事は、利用者の心と体のケアをする重要な役割を担います。そのため、単に資格を持っているだけではなく、向き・不向きも大きく影響するでしょう。ここでは、どのような人がセラピストに向いているのかを紹介します。
人と接することが好き
セラピストの仕事は、相談者と対話を重ねながら信頼関係を築くことが不可欠です。そのため、人と関わることを楽しめる人にとっては、大きなやりがいを感じられる仕事ではないでしょうか。
というのも、日々さまざまな相談者や利用者と向き合う中で「人と話すのが楽しい」「相手に興味を持てる」という気持ちがあると、無理なくコミュニケーションを続けられるからです。
また、人と接することが好きな人は、会話の中で自然と関心や好奇心を持ちやすく、「もっと知りたい」という気持ちで接することになり、相手が話しやすい雰囲気をつくることも得意でしょう。
とくに相談者の中には、不安や悩みを抱え、自分の気持ちをうまく言葉にできない人もいます。そうした相手を支え、気持ちを整理し、前向きな方向へ導くことができる人は、セラピストに向いていると言えます。
共感力に長けている
セラピストは、相談者や利用者が抱える悩みや不安を正確に理解し、それに共感できる力が必要です。ただ話を聞くだけではなく、相手の心情や背景にある問題を深く読み取る力が求められるでしょう。
さらに、共感力が高いと利用者は「自分の気持ちを分かってくれる」と感じ、安心して心を開くことができます。
しかし、ただ共感するのではなく冷静に状況を見極め、適切なアドバイスやサポートができるバランス感覚も重要です。
人のために何かをすることが好き
セラピストの仕事は、相談者や利用者の悩みに寄り添い、より良い方向へ導くサポートをすることです。そのため、「誰かの役に立つことに喜びを感じる」人には非常に向いていると言えます。
例えば、見返りを求めるのではなく「純粋に人の助けになりたい」という気持ちが強い人ほど、セラピストとしてのやりがいを感じられるはずです。
また、相手によってはすぐに結果が出ないこともありますが、それでも根気強く支援を続けられる忍耐力も必要となるでしょう。
メンタルが安定している
セラピストの仕事は、相談者や利用者の深刻な悩みに直面する機会が多いため、自分自身のメンタルが安定していることが大切です。
相手の感情に深く入り込みすぎると、自分まで影響を受けてしまい、セラピストとしての冷静な判断が難しくなることがあります。そのため、共感しつつも一定の距離感を保ち、感情に振り回されない強さが求められます。
また、利用者の変化がすぐに見られない場合や、うまく信頼関係を築けない場面もあるため、落ち込まずに前向きに対応できる精神力も必要です。
臨機応変な対応に自信がある
セラピーの現場では、想定外の事態が起こることも少なくありません。
相談者や利用者によって性格や悩みの内容は異なり、同じアプローチが全ての人に通用するわけではないため、その場の状況に応じた柔軟な対応力が求められます。
また、相手の気分や状態が都度変化することも多いため、計画通りに進めることにこだわりすぎず、必要に応じて臨機応変にアプローチを変えることができるかどうかも重要なポイントです。
このように相手に合わせた適切な対応ができる人は、セラピストとしての信頼を得やすくなるでしょう。
セラピーは種類に関係なくやりがいのある仕事!
セラピーにはさまざまな種類がありますが、どの分野でも共通しているのは「人の心や体を癒し、支える仕事である」という点です。
医療系のセラピーは治療の一環として活用され、ボディ系は身体のコンディションを整え、メンタル系は心のケアを行い、リラクゼーション系は日々の疲れを和らげます。それぞれの役割は異なりますが、どの分野も人々の生活を豊かにする大切な仕事です。
私たち日本保健福祉ネイリスト協会は、2012年の活動開始以来、福祉ネイルという美容を通じて高齢者の方々が輝きある日々を送れるようサポートしてきました。
施術ではネイルケアに加え、ハンドトリートメントも取り入れております。これは治療を目的としたマッサージとは違って、リラクゼーションを重視したものです。効果としては、血行促進や油分補給、リラックス、大脳の活性化、指先の運動促進などが期待でき、利用者様からも心身ともにくつろげると好評をいただいております。
また、施術の際には脳の若返りが期待できるアロマの香りで嗅覚を刺激したり、高保湿のクリームで水分と油分を補給することで、しっとりとした健やかな肌へと導くことも高齢者の方に喜ばれる理由の一つです。
なお、当協会では福祉ネイリストを目指す方に向けたスクールを運営し、北海道から九州まで全国に展開しております。
ご興味のある方は、ぜひ日本保健福祉ネイリスト協会で専門的な知識と技術を学び、新たなセラピーの道を切り開いてみてください。
福祉ネイリスト、認定校、資料請求などのご相談・お問い合わせはこちらから