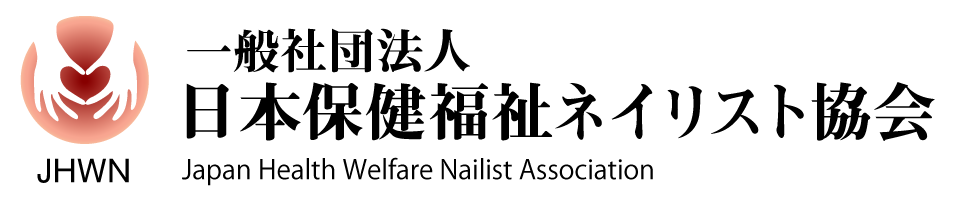高齢者とのコミュニケーションにおすすめの方法は?コツや注意点も紹介!

介護施設などで高齢者の方と接する際に「コミュニケーションが上手く取れない」と悩む方は多いのではないでしょうか?
より良い介護をするためには、高齢者の方とのコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことが大切です。
そこで本記事では、高齢者とのコミュニケーションにはどんなものがあるか、上手くコミュニケーションをとるコツや注意点などを詳しく紹介していきます。
目次
高齢者にコミュニケーションが必要な理由
介護において高齢者の方とコミュニケーションを取ることは、高齢者の方への理解を深めて信頼関係を築くために必要です。そうすることで、より良い介護やケア、事故などのアクシデントを未然に防ぐことにも繋がります。
一般的に高齢者の方は、人に会ったり身体を動かす機会が減っていくことから、脳への刺激が少なくなると言われています。そのため、コミュニケーションを取ることは、その人の考えや感情に刺激を与えたり、誰かに会うために立つ・歩くなどの身体を動かすことへと繋がるので、脳が活性化されて認知症予防や健康維持に役立つのです。
また、人と交流することで悩みや不安を打ち明けたり、昔話に花を咲かせたりと、一人でいる時よりも孤独を感じにくくなり、「ストレス解消」「生きがいの再発見」などの効果も得られます。
このように、高齢者の方にとってコミュニケーションを取ることは、身体的にも心理的にもとても良い効果が期待できる介護現場においては欠かせないものと言えるでしょう。
高齢者とコミュニケーションを取る2つの方法
はじめに、高齢者の方とコミュニケーションをとる方法として、次の2つの方法があることを知っておきましょう。
- 言語コミュニケーション
- 非言語コミュニケーション
高齢者の方とのコミュニケーションに悩んでいる方は、これらの違いを知った上で使い分けてみてください。
言語コミュニケーション
言語コミュニケーションとは、言葉を使ってコミュニケーションをとる手法のことで、話す・聞くなど言葉を用いて意思を伝えるものです。
この言語コミュニケーションには大きく分けて3つの種類があります。
- 音声言語:口から発するもの
- 筆談言語:文字によるもの
- 手話言語:手や体の動きによるのもの
中でも一般的に皆さんがよく使う言語コミュニケーションは「音声言語」ですね。
音声言語でコミュニケーションをとるためには、「喋る・聞く・理解する・考える」といった4つの力が必要になります。しかし、高齢者の方の中にはこれらの力が低下している方もいるため、一緒に過ごす高齢者の方によって、言葉遣いや話し方を変え、伝わりやすくすることが非常に重要です。
また、「言葉」は、だれもが使える便利なコミュニケーション手段である一方、使い方に注意しなければ簡単に相手を傷つけてしまうこともあります。
たとえ言葉でのコミュニケーションが難しい高齢者の方が相手でも、乱暴な言葉というものは、表情や声のトーンによって必ず伝わるものなので、言葉遣いには気をつけてください。
非言語コミュニケーション
非言語コミュニケーションとは、言葉以外でコミュニケーションをとる手法です。表情や声のトーン、ジェスチャー、アイコンタクトなどを用いて意思や気持ちを伝えることで、会話がスムーズにいかないときでも意思疎通がしやすくなるという特徴があります。
非言語コミュニケーションが与える印象というのは非常に大きく、じつは言葉よりも自分の気持ちが伝わりやすいとされているのです。
ここで、人と人がコミュニケーションをとるときに、どんな情報が他人に影響を与えるのかを示した数値があるので簡単に紹介しましょう。
- 言語情報:7%
- 聴覚情報:38%
- 視覚情報:55%
この割合はメラビアンの法則といい、コミュニケーションにおいて言語・聴覚・視覚がどれくらいのウェイトで伝達に影響するかを表す心理学の法則の1つです。
メラビアンの法則からも分かるように「文字<声<見た目」という順で、相手に自分の思考や気持ちが伝わるということがわかりますね。
つまり、会話に頼り切らなくてもコミュニケーションが取れることを意味しており、耳が遠い高齢者の方、認知機能が低下した高齢者の方と接する際にも非常に役立つでしょう。
具体的に、介護現場で非言語コミュニケーションを行う際は、穏やかな笑顔で接し、話を聞くとき相槌をうったりうなずいたりして「あなたの話に興味があります」というように、介護従事者自身が楽しむ姿を見せることがポイントです。そうすると相手もきっと楽しんでくれるでしょう。
また、高齢者の方の体の一部に優しく触れることも非言語コミュニケーションの一つとしておすすめですが、体を触られるのが嫌な方もいるので、スキンシップをする際は、高齢者それぞれの個性に合わせて使い分けてくださいね。
高齢者とのコミュニケーションを上手に取る5つのコツ
ここからは、コミュニケーションを上手に取るコツを紹介していきます。基本的には「相手の立場になって言動すること」が重要ですが、具体的には次のようなことを押さえておきましょう。
- 声のトーンを意識する
- 目線の高さに気を付ける
- 聞き手上手になる
- 発言を急がせない
- 沈黙に慣れる
それでは一つずつ詳しくみていきます。
温かい声のトーンで話す
高齢者の方と話をする際は、こちらの話していることが聞き取りやすいように次のことを意識して話してみましょう。
- 声のトーンは低く、温かみのある声で話す
- 相手のスピードに合わせて話す
- 口をしっかりと動かしはっきりと発音する
- 言葉に区切りをつけて話す
高齢者になると、耳が遠くなったり認知機能の低下により、私たちが日常的に話す声の大きさや速さでは聞きとりにくくなります。
例えば、小さい声、大きすぎる声、高い声、早口、カ行・サ行・タ行・パ行が聞き取りにくいとされていることはご存知ですか?
とくに60歳を超えると電子音のような高音が聞き取りづらくなるため、声が高い女性の介護士の方の中には「大きな声でしゃべっているのになかなか意思疎通ができない」と悩む方もいるのです。
また、聞こえやすいようにと大きな声で話してしまいやすいですが、高齢者の方からすると耳元での大声に驚いたり不快に感じることもあるので気をつけましょう。
大きな声で話すよりも、声のトーンを低くして笑顔で「今日は/天気が/良いですね」というように言葉に区切りをつけて話してみましょう。そうすることで、高齢者の方も聞き取りやすく会話そのものを楽しむことができるようになります。
目線・目線の高さを合わせて話す
高齢者の方とコミュニケーションをとる際は、目線を合わせることはもちろん、相手の目線の高さに合わせて話をするようにすることも大切です。
とくにベッドで寝ている状態の方や、車いす生活の方に話しかける場合、立ったままの姿勢だと高齢者の方を上から見下ろす形になり、高圧的・威圧的に感じてしまう方もいるかもしれません。
また、高齢者の方の横や後ろから突然話しかけるのもNGです。驚いてケガをしてしまっては危ないので、必ず正面から話しかけるようにしてください。
同じ高さもしくは低い位置から話すことによって、より口の動きや表情もはっきりと見え、言葉が聞き取りやすく気持ちも伝わりやすくなるでしょう。
聞き手になる
高齢者の方とのコミュニケーションを取る際は、聞き手になることを意識してみてください。
介護スタッフが高齢者の方の話を親身になって聞くことで、言語能力が低下していても「誰かに自分の意志を伝えたい」「誰かとおしゃべりすることが楽しい」という気持ちになりやすいのです。また、喋ること自体が脳の活性化にも繋がりるため、認知症の予防にも繋がります。
聞き上手になるためには、相手の話を傾聴することがポイントなのですが、具体的には次のことを意識してみてください。
- 相手の目を見ながら頷く
- 会話の合間に相槌を打つ
- 相手の気持ちになって共感する
- 否定や批判はしない
このことを踏まえたうえで、話すときの表情や声のトーンもしっかりと確認しながら傾聴すると、さらに良いでしょう。
高齢者の方が「ちゃんと聞いてくれている」と安心するだけでなく、どんなことに不安を感じ、どんな話のときが楽しそうかなど、相手のことを理解するためにも、聞き手になることは介護においてとても良いコミュニケーションの取り方だと言えてるでしょう。
相手の発言を急がせない
高齢者の方によっては、老化の進行や病気が原因で「言葉がすぐに出てこない」「声が出にくい」といった言語障害を持つ人もいます。
そのような場合、言葉が出てくるのを急かしたり、話を遮ってしまわないようにしてください。
本当は言いたいことがあるのに、急かされると混乱したり、自尊心を傷つけられたと思うかもしれないからです。
そうなると高齢者の方はさらに自分に自信がなくなり、なかには塞ぎ込んでしまう方もいるでしょう。忙しい介護現場ではありますが、まずは相手のスピードに合わせてコミュニケーションをとるようにすることが大切です。
沈黙を気にしない
高齢者の方と話をしていると途中で会話が途切れたり、言葉が出てこず沈黙が続くときがあります。
そんなときは、慌てて次の話題を探すのではなく、沈黙に慣れることがポイントです。無理に会話を続けても、かえって高齢者の方の負担になってしまう可能性もあるからです。
また、なかには会話が苦手な方や、その日は話をする気分ではないという方、脳梗塞などの病気によりコミュニケーションを取るのが難しい方もいます。
沈黙にはさまざまな理由があるため、無理に会話を続けようと話を振る必要はないのです。しばらく隣に座ったり、一緒に散歩して同じ時間を過ごすだけでも問題ありません。
高齢者の方の様子や表情をしっかりと見て、居心地の良い時間を過ごしてもらえるように考えれば、沈黙を恐れる必要はないでしょう。
高齢者とのコミュニケーションがうまくいかない時のポイント・注意点
高齢者の方と上手にコミュニケーションをとるコツを押さえて接していても、うまくいかないときもあります。そんなときは、次のことを改めて確認してみてください。
- 病気に対する正しい知識はあるか
- 特別視していないか
これらは高齢者の方と関わる上で欠かせないポイントです。1つずつ確認しましょう。
認知症などの病気に対して正しい知識を持っているか
高齢者の方とコミュニケーションをとる前に、認知症や脳梗塞などの病気について正しい知識を身につけることが大切です。
これらの病気が「どんな症状なのか」「なぜそうなってしまうのか」をきちんと理解していなければ、うまくコミュニケーションが取れないだけでなく、高齢者の方の気持ちを傷つけてしまうことになるかもしれません。
例えば、高齢者の中でも多いと言われている認知症には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか?物忘れ・記憶力の低下が起こる「アルツハイマー型認知症」、歩行障害・手足のしびれなどの症状が出る「血管性認知症」など、認知症と一言に言っても、種類によって症状が全く違うのです。
そのため「思うように身体が動かせない」「さっきまでのことが思い出せない」など、悩みや不安も様々あり、それぞれにあった方法のコミュニケーションを見つけていくことが重要だと言えます。
特別視していないか
高齢者の方とコミュニケーションを取る際「高齢者だから」「認知症だから」「車椅子生活だから」という理由で、頑固で怒りっぽい、会話が続かない、動きたがらないというように特別視していませんか?
高齢者の方の病気や症状を理解することは大切ですが、知識を持って接することと、病気だから可哀想など特別視して接することでは、相手が感じる気持ちに違いが生まれます。
特別視することで、相手の自尊心を傷つけてしまったり、信頼関係が築けないまま一緒に過ごすことになるかもしれません。
そのため、まずは一緒に過ごす高齢者の方について「どんな悩みがあり、どんなことに興味があるのか」などを知った上で、その人に合ったコミュニケーション方法を見つけていきましょう。
なお、相手のことを知る際は「回想法」という心理療法の一種を使ってみるのがおすすめです。
回想法とは?
回想法とは、昔の思い出や出来事を振り返り、楽しい気持ちを思い出したり、自分が大切な存在であることを再認識することで、精神的な安定を得ながら孤独感を和らげる方法です。
また、昔のことを思い出すことは脳の活性化にも繋がるため、認知症の予防にも繋がるとされています。
この回想法を用いれば、高齢者の方の好き嫌いや、どんな風に話をするのか、昔と比べて何に不安・不満を感じているのかが見えてくるはずです。
高齢者一人ひとりに合う接し方を見つけていくことができれば、今よりももっと信頼関係ができ、高齢者の方とコミュニケーションを取ることが楽しくなるでしょう。
高齢者と上手くコミュニケーションをとって信頼関係を築こう
高齢者の方とのコミュニケーションを上手に取ることは、より良い介護をするために必要不可欠です。本記事では、声のトーンや大きさ、相手の話を否定しない、急かさないなどさまざまなコツを紹介しました。これらのことを意識しながらコミュニケーションを図り、高齢者の方と信頼関係を築いていきましょう。
私たち日本保健福祉ネイリスト協会では、2012年の活動開始以来、福祉ネイルという美容を通じて、高齢者の方が輝きある日々を送れるようサポートしてきました。
高齢者の方にネイルを行う際は、「回想法」と言う心理学からくる会話方法をコミュニケーションとして使っており、施術中も楽しんでいただけるよう工夫しています。
また、回想法を用いた福祉ネイルで、もっと多くの高齢者の方の笑顔が増えるよう、福祉ネイリストの育成や福祉ネイルの研究集会にも力を入れています。
「施設に美容サービスを導入したい」とお考えの際は、ぜひ日本保健福祉ネイリスト協会にご相談ください。
福祉ネイリスト、認定校、資料請求などのご相談・お問い合わせはこちらから